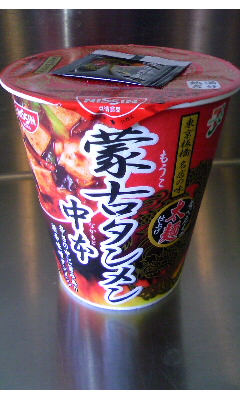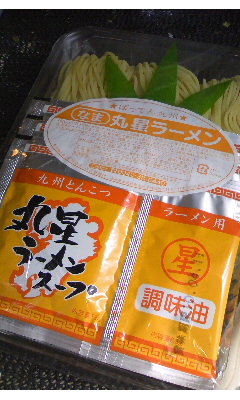2008年12月31日
2008年ゆく麺くる麺ラーメンコラムvol.2
まぁ整理といっても、これはあくまでもオイラの持論をふまえてのことで、内容を保証出来るものでは無いが、今まで大分のラーメン店を回った中、店主に聞いた話や歴史書、新聞、雑誌などの色々な書物を調べた中からオイラなりにまとめたものである。
(≧∇≦)ゞ
ご存知のように九州の中でも大分には「ご当地ラーメン」と呼ばれている物が無い。
福岡には「博多ラーメン」や「久留米ラーメン」「長浜ラーメン」、熊本の「熊本ラーメン」「玉名ラーメン」、鹿児島の「鹿児島ラーメン」、沖縄には「沖縄そば」があり、宮崎の「宮崎ラーメン」、佐賀の「佐賀系ラーメン」(こいつはちょっと微妙だが‥)、長崎にはその歴史も古く、1899年(明治32年)に中華料理の老舗『四海楼』で陳平順氏が考案した「長崎チャンポン」(当時は支那うどんと呼ばれていた)というその地方特色の麺文化が存在する。
大分にも古くから「ほうちょう」や「やせうま」という麺はあるが、これはラーメンのような形態の文化では無く、いってみれば郷土料理の一つに値する。
他に「日田焼そば」や「別府冷麺」という誇れる麺もあるのだが、決して日本中に有名な食べ物というわけではないだろう。
( ^ ^ ;)
九州のラーメンの歴史をさかのぼれば、1937年(昭和12年)、もともとはうどんの屋台をひいていた宮本時男氏が「支那そば」の噂を聞きつけ、横浜南京街へ出向き修行を積み、九州では初のラーメン屋台『南京千両』が久留米で営業開始したのはご存知の通り。
当時のスープは豚骨のみを煮込み、今の久留米ラーメンのような濃く白濁したスープというより、やや透明度のある茶濁に近いあっさりとした状態だったようだ。
( ^ ^ )
福岡では1941年(昭和16年)、福岡市博多区の今は無き玉屋デパート横に開業した「三馬路」(ここから「五馬路」が独立し、現在の「うま馬」になる)が福岡初のラーメン屋台。
澄んだ豚骨の清湯スープで、今の博多ラーメンというスタイルのものではなかったようである。
その後、1947年(昭和27年)に白濁豚骨スープの元祖『三九』が支那ソバ系の清湯スープで開店したものの、釜の火加減のミスから煮えたぎった白濁スープが生まれ、九州の白濁豚骨スープスタイルが定着したという話は有名なところ。
(●^o^●)
(≧∇≦)ゞ
ご存知のように九州の中でも大分には「ご当地ラーメン」と呼ばれている物が無い。
福岡には「博多ラーメン」や「久留米ラーメン」「長浜ラーメン」、熊本の「熊本ラーメン」「玉名ラーメン」、鹿児島の「鹿児島ラーメン」、沖縄には「沖縄そば」があり、宮崎の「宮崎ラーメン」、佐賀の「佐賀系ラーメン」(こいつはちょっと微妙だが‥)、長崎にはその歴史も古く、1899年(明治32年)に中華料理の老舗『四海楼』で陳平順氏が考案した「長崎チャンポン」(当時は支那うどんと呼ばれていた)というその地方特色の麺文化が存在する。
大分にも古くから「ほうちょう」や「やせうま」という麺はあるが、これはラーメンのような形態の文化では無く、いってみれば郷土料理の一つに値する。
他に「日田焼そば」や「別府冷麺」という誇れる麺もあるのだが、決して日本中に有名な食べ物というわけではないだろう。
( ^ ^ ;)
九州のラーメンの歴史をさかのぼれば、1937年(昭和12年)、もともとはうどんの屋台をひいていた宮本時男氏が「支那そば」の噂を聞きつけ、横浜南京街へ出向き修行を積み、九州では初のラーメン屋台『南京千両』が久留米で営業開始したのはご存知の通り。
当時のスープは豚骨のみを煮込み、今の久留米ラーメンのような濃く白濁したスープというより、やや透明度のある茶濁に近いあっさりとした状態だったようだ。
( ^ ^ )
福岡では1941年(昭和16年)、福岡市博多区の今は無き玉屋デパート横に開業した「三馬路」(ここから「五馬路」が独立し、現在の「うま馬」になる)が福岡初のラーメン屋台。
澄んだ豚骨の清湯スープで、今の博多ラーメンというスタイルのものではなかったようである。
その後、1947年(昭和27年)に白濁豚骨スープの元祖『三九』が支那ソバ系の清湯スープで開店したものの、釜の火加減のミスから煮えたぎった白濁スープが生まれ、九州の白濁豚骨スープスタイルが定着したという話は有名なところ。
(●^o^●)
こうして生まれた『三九』の白濁豚骨スープが縁戚関係により、佐賀、北九州、大分、また熊本の玉名にと引き継がれていったわけである。
話はそれたが、では『大分ラーメン』という名前は無いまでも、県の北、南、西と食べ歩き、明らかにその傾向に違いが見えて来る。
オイラが感じるに大分のラーメンの系統、また老舗に関してみれば、大きく分けて3つに分かれるようだ。
その一つが、佐伯系と言われるラーメン。
独特なニンニクの香りに存在感のある太麺の組み合わせは、実に豪快である。
( ̄ー+ ̄)
今のところ代表的な老舗としては、『上海(閉店)』、『香蘭』、『藤原来々軒』などがあげられるが、残念なことにオイラが調べた中ではそれ以前の歴史がわからない。
(―.― ;)
ルーツはどうやら中華料理店にありそうな感じのことも聞いたがまだまだ謎、この佐伯系ラーメンの歴史にいたっては来年の課題としょう。
(=゜-゜)(=。_。)
続いて、県北を代表する昭和33年創業の老舗『中津 宝来軒』である。
!(b^ー°)
山平氏により始まる県北系の味は、豚骨、鶏ガラ、牛骨の三種の骨を使用する甘味のあるスープが特徴。
県内でも直営店は数店舗あり、暖簾わけの「宝来軒」も多数存在する。
親戚筋にある『宝来軒 万田店』の息子さんは東京の高田馬場に『大分宝来軒』を出店、電話で軽い取材をさせていただいたが、実に親切な方である。
(≧∇≦)ゞ
また別府の『宝来軒(閉店)』や、その後に続く創業昭和37年の『ニュー宝来』も『中津 宝来軒』の山平氏の縁戚にあたるらしい。
P博多とんこつラーメン((株)めん食)
産経新聞 それゆけ!大阪ラーメン(エースコック(株))
ふるる冷麺 辛口【ビビン冷麺】(農心)
ヤクルトラーメン 麺許皆伝 みそ味((株)ヤクルト)
ペヤング 味の大関 しお味(まるか食品(株))
黒豚ラーメン((株)益田製麺)
産経新聞 それゆけ!大阪ラーメン(エースコック(株))
ふるる冷麺 辛口【ビビン冷麺】(農心)
ヤクルトラーメン 麺許皆伝 みそ味((株)ヤクルト)
ペヤング 味の大関 しお味(まるか食品(株))
黒豚ラーメン((株)益田製麺)
Posted by ラーメン聖人 at 13:13│Comments(0)
│ラーメンコラム・他