2009年09月06日
ラーメン夜明け前・歴史に想いを馳せるVol.3(コラム)
《ラーメン夜明け前・歴史に想いを馳せるVol.2より続き》
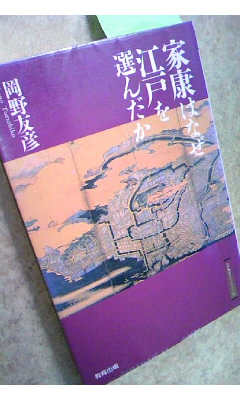
これの全てを鵜のみにするには読んだ文面が多少偏り過ぎているような気もするが、葦原が生い茂る小さな漁村でおおよそ現代の東京、いや栄えた江戸文化からははなはだ遠いイメージの土地だったということは十分に想像できる範囲である。
( ^ ^ )
実際のところ、江戸を選んだのが家康だったのか、いや秀吉より江戸を選ばされたということだったのかはいくつかの逸話があるのだが、ラーメン史からみれば、これはどちらでもよいことで、要は家康が江戸の地に幕府を開いたことが重要になってくるのである。
というのも江戸が大都市になり得た理由は、単に政治の中心だったからというわけではないよである。
( ̄ー+ ̄)
あえて江戸を本拠地としたのは、関東平野という広大な後背地と水運の便に恵まれ、将来への発展の可能性を秘めていたことに着目したからに他ならないのでないだろうか。
( ^ ^ )
因みに、『家康はなぜ江戸を選んだか』では、この解釈については否定的に書かれているのだが‥
( ^ ^ ;)
まぁ、あくまでもオイラが個人的に心地よい解釈、もしくは一番多くの書物に書かれてあった説を紹介させていただくことにしているわけで‥
どちらにしてもオイラ、たしか江戸幕府はこの地で264年もの長い間続いたと記憶している。
これも江戸に幕府を開いた家康に先見の明があったということになるのではないだろか。
( ̄ー ̄)v
現に江戸時代になると多くの名物や特産品が生まれている。
町の経済は発達しながら町人文化も発展してきたようだ。
その中から「外食」が生まれてきたのだ。
!(b^ー°)
『江戸の料理と食生活』原田信男・編(小学舘)では徳川家康をもてなした織田信長の饗応料理から庶民の食事、人気のメニュー、台所事情まで当時の料理文化や食生活が写真や浮世絵、風刺画をとおして眺めることが出来る。
(* ^^ *)
 続きを読む
続きを読む
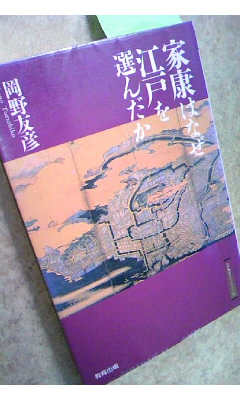
これの全てを鵜のみにするには読んだ文面が多少偏り過ぎているような気もするが、葦原が生い茂る小さな漁村でおおよそ現代の東京、いや栄えた江戸文化からははなはだ遠いイメージの土地だったということは十分に想像できる範囲である。
( ^ ^ )
実際のところ、江戸を選んだのが家康だったのか、いや秀吉より江戸を選ばされたということだったのかはいくつかの逸話があるのだが、ラーメン史からみれば、これはどちらでもよいことで、要は家康が江戸の地に幕府を開いたことが重要になってくるのである。
というのも江戸が大都市になり得た理由は、単に政治の中心だったからというわけではないよである。
( ̄ー+ ̄)
あえて江戸を本拠地としたのは、関東平野という広大な後背地と水運の便に恵まれ、将来への発展の可能性を秘めていたことに着目したからに他ならないのでないだろうか。
( ^ ^ )
因みに、『家康はなぜ江戸を選んだか』では、この解釈については否定的に書かれているのだが‥
( ^ ^ ;)
まぁ、あくまでもオイラが個人的に心地よい解釈、もしくは一番多くの書物に書かれてあった説を紹介させていただくことにしているわけで‥
どちらにしてもオイラ、たしか江戸幕府はこの地で264年もの長い間続いたと記憶している。
これも江戸に幕府を開いた家康に先見の明があったということになるのではないだろか。
( ̄ー ̄)v
現に江戸時代になると多くの名物や特産品が生まれている。
町の経済は発達しながら町人文化も発展してきたようだ。
その中から「外食」が生まれてきたのだ。
!(b^ー°)
『江戸の料理と食生活』原田信男・編(小学舘)では徳川家康をもてなした織田信長の饗応料理から庶民の食事、人気のメニュー、台所事情まで当時の料理文化や食生活が写真や浮世絵、風刺画をとおして眺めることが出来る。
(* ^^ *)
 続きを読む
続きを読む2009年09月06日
ラーメン夜明け前・歴史に想いを馳せるVol.2(コラム)
《ラーメン夜明け前・歴史に想いを馳せるVol.1より続き》
やがて朱舜水の名声は水戸藩主徳川光圀(水戸黄門)の知るところとなり、1665年(寛文5年)、江戸の上屋敷で対面することとなるのだ。
( ^ ^ )

[昭和ラーメン風(別府市)]
その後、「光圀は、朱舜水を先生として仰ぎ、藩政や学問思想に大きな影響を受けた」書かれている。
朱舜水が没したのはこれから17年後のことであるからして、対面以降の光圀との関係はかなり親しいものだったろうと想像させていただいた。
(* ^^ *)
ところで、光圀にはウドンを打つという藩主にはあまり似つかわしくない趣味があったことをご存知だろうか?
( ^ ^ ;)
当然、親しい間柄なら光圀は自前の手打ちウドンを振る舞ったにちがない。
また、お礼に朱舜水も明の麺料理でこたえたはずである。
これは想像の範囲をこえるものではないが、17年の間、幾度となく繰り返されたと想像してもおかしくはないだろう。
(^。^ ;)?
朱舜水から光圀への献上品の記述の中に「藕粉(オウフェン)」「火腿(フォタイ)」といったものが含まれていた。
「藕粉」とはレンコンの粉で鹹水の代わりとなるらしい。
「火腿」は塩漬けにした豚肉のハムの一種。
一般的にスープの味付けなどに使われるポピュラーな食材である。
このような記述から「日本で最初にラーメンを食べたのは水戸黄門である!」というような説が生まれてきたのだ。
(* ^^ *)
しかしながら、オイラが読んだ書物の中においては、その証拠や断言しているものはなく、あくまでも一説という書き方がされているわけで、やはり、想像の域はこえられそうもないようである。
( ^ ^ ;) 続きを読む
やがて朱舜水の名声は水戸藩主徳川光圀(水戸黄門)の知るところとなり、1665年(寛文5年)、江戸の上屋敷で対面することとなるのだ。
( ^ ^ )

[昭和ラーメン風(別府市)]
その後、「光圀は、朱舜水を先生として仰ぎ、藩政や学問思想に大きな影響を受けた」書かれている。
朱舜水が没したのはこれから17年後のことであるからして、対面以降の光圀との関係はかなり親しいものだったろうと想像させていただいた。
(* ^^ *)
ところで、光圀にはウドンを打つという藩主にはあまり似つかわしくない趣味があったことをご存知だろうか?
( ^ ^ ;)
当然、親しい間柄なら光圀は自前の手打ちウドンを振る舞ったにちがない。
また、お礼に朱舜水も明の麺料理でこたえたはずである。
これは想像の範囲をこえるものではないが、17年の間、幾度となく繰り返されたと想像してもおかしくはないだろう。
(^。^ ;)?
朱舜水から光圀への献上品の記述の中に「藕粉(オウフェン)」「火腿(フォタイ)」といったものが含まれていた。
「藕粉」とはレンコンの粉で鹹水の代わりとなるらしい。
「火腿」は塩漬けにした豚肉のハムの一種。
一般的にスープの味付けなどに使われるポピュラーな食材である。
このような記述から「日本で最初にラーメンを食べたのは水戸黄門である!」というような説が生まれてきたのだ。
(* ^^ *)
しかしながら、オイラが読んだ書物の中においては、その証拠や断言しているものはなく、あくまでも一説という書き方がされているわけで、やはり、想像の域はこえられそうもないようである。
( ^ ^ ;) 続きを読む
2009年09月06日
ラーメン夜明け前・歴史に想いを馳せるVol.1(コラム)
今朝、何気なくつけたテレビに‥
ん?‥( ̄○ ̄;)‥
どこかでお会いしたような方が‥
Σ( ̄□ ̄;)!! なっ!
なんと、[かばの部屋~新館~]でお馴染みの『かばさん』ではないか!!
( ^ ^ ;)
相変わらず凄い知名度ですねぇ~♪
本日、OBSのカボスタイムに出演され、blogの書き方指南をされている彼女。
もっぱらラーメンオンリーで拙い記事を書きなぐっているオイラなんぞには、知名度なんて無に等しいのだが、わずか二年そこらで九州でも上位ランキングに入るblogサイトに育てられるとは、実に凄いとしか言いようがない。
( ^ ^ )
特にカメラワーク、画像処理には素晴らしいものがあり、オイラの携帯画像&化石化寸前のデジカメなんぞは足元にも及ばないのである。
( ^ ^ ;)
ここは一発!文章力で!!などと無いものを言っても仕方ないので、やはりオイラはほそぼそとブロガー達の片隅で頑張っていこうと誓った今朝である。

[チャイナダイニング敦煌(臼杵市)]
さてさて、前回の日曜日には『麺の誕生・歴史に想いを馳せる』という拙い記事を書かせていただいたわけだ。
今回は、この続きというべきか中華麺が日本に渡りラーメンの夜明け前までをまたまた、かいつまんで書かせていただくことにしよう。
( ^ ^ )
あくまでも、オイラがたいして無い頭脳を使って一週間、調べた十数冊の書物からまとめて書いているわけで、説は諸説ある場合が多い。
続きを読む
ん?‥( ̄○ ̄;)‥
どこかでお会いしたような方が‥
Σ( ̄□ ̄;)!! なっ!
なんと、[かばの部屋~新館~]でお馴染みの『かばさん』ではないか!!
( ^ ^ ;)
相変わらず凄い知名度ですねぇ~♪
本日、OBSのカボスタイムに出演され、blogの書き方指南をされている彼女。
もっぱらラーメンオンリーで拙い記事を書きなぐっているオイラなんぞには、知名度なんて無に等しいのだが、わずか二年そこらで九州でも上位ランキングに入るblogサイトに育てられるとは、実に凄いとしか言いようがない。
( ^ ^ )
特にカメラワーク、画像処理には素晴らしいものがあり、オイラの携帯画像&化石化寸前のデジカメなんぞは足元にも及ばないのである。
( ^ ^ ;)
ここは一発!文章力で!!などと無いものを言っても仕方ないので、やはりオイラはほそぼそとブロガー達の片隅で頑張っていこうと誓った今朝である。

[チャイナダイニング敦煌(臼杵市)]
さてさて、前回の日曜日には『麺の誕生・歴史に想いを馳せる』という拙い記事を書かせていただいたわけだ。
今回は、この続きというべきか中華麺が日本に渡りラーメンの夜明け前までをまたまた、かいつまんで書かせていただくことにしよう。
( ^ ^ )
あくまでも、オイラがたいして無い頭脳を使って一週間、調べた十数冊の書物からまとめて書いているわけで、説は諸説ある場合が多い。
続きを読む



